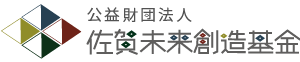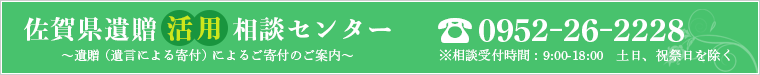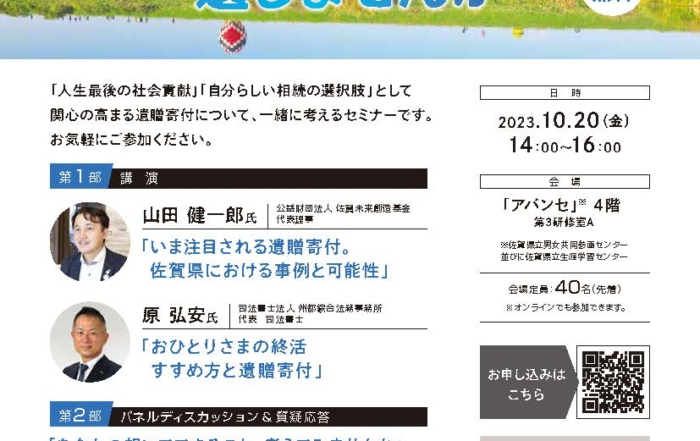佐賀未来創造基金の遺贈相談窓口
佐賀県遺贈寄付活用相談センター
全国レガシーギフト協会に加盟して「いぞうの窓口」を担っています。
あなたの想いを未来へつなぐ―遺贈寄付
遺贈寄付とは、自分が亡くなったときに、遺言によって財産の全部または一部を非営利団体・公益団体等に寄付することを言います。
近年、社会貢献への関心が高まるなか、人生の集大成として「自分の遺産を社会のために活かしたい」と考える方が増え、この遺贈寄付が注目を集めています。
遺贈寄付の遺贈先はご自分で選択することができ、遺贈を受けた団体は、地域の課題解決に取り組むための活動を継続・発展させることができます。一方で、その恩恵を最も受けるのは、支援を必要とする子どもたちや高齢者、被災者など、地域社会で暮らす人々です。
あなたのあたたかな想いが未来の誰かの希望になり、そうした変化の積み重ねが、よりよい社会の実現につながっていきます。
"人生のしめくくり" 遺贈寄付で託す自己実現

世の中にはさまざまな社会課題があり、さまざまな団体がその解決に向けた活動を展開しています。
通常の寄付行為の場合、その団体の理念や活動に共感し、「このようになってほしい」、「こんな社会になったらいい」という想いを元に寄付や支援を行う。つまり、自分が望む未来を選択して寄付をしていると言えます。
そして、遺贈寄付の場合、自分が亡くなった後の寄付であるがゆえに、「自分が寄付をした結果」を自分で確認することはできません。
それでも、自分の遺産を使って、あるべき「未来の社会変化を期待して託す」行為は、なおさら究極な自己実現、「自己超越」の領域にあると言えます。
遺贈寄付の活用方法
遺贈寄付の事例紹介
佐賀県鹿島市で、生前 日本舞踊の先生をされていた故 中島鈴子さんの「地域にお世話になったので、恩返しをしたい」という想いと共にご自宅(不動産)と金銭の遺贈を受けました。
1.不動産:地域活動の拠点として活用
地域の災害拠点として、また、地域団体による子ども食堂を開催するためのスペースとして活用しています。
2.金銭:基金創設と助成事業の実施
中島鈴子さんの想いから、「鹿島レガシー基金」を創設し、地域における「伝統芸能」「地域おこし」「地域文化の継承」活動等に対する助成事業を実施しています。
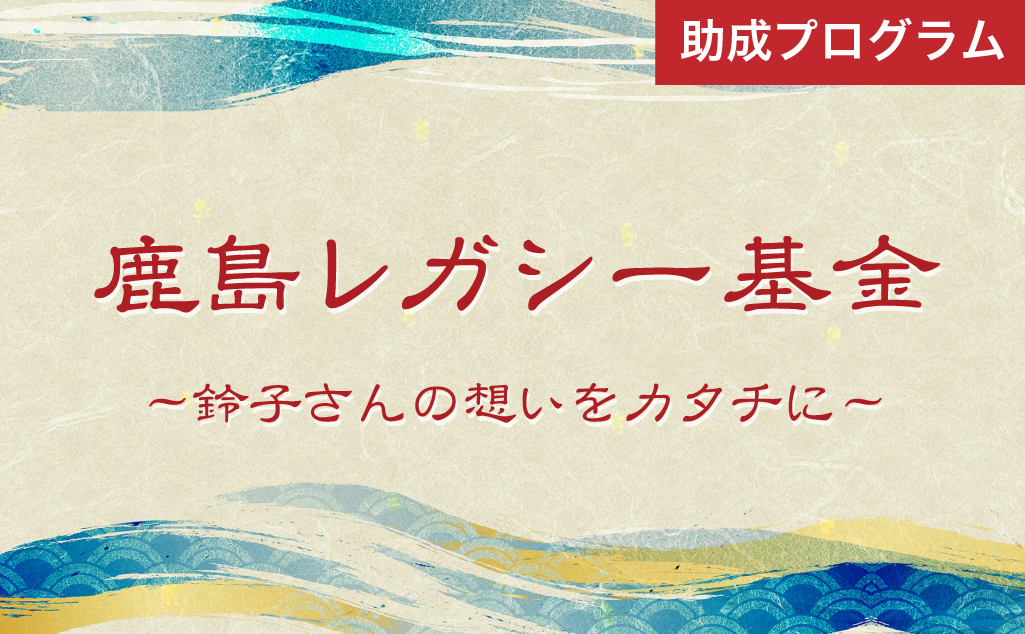
遺贈寄付の流れ-ステップ
1.全体像を把握するための相談
まずは、ご自身の考えや、遺贈寄付がどのように自分の意図とマッチするかを相談することをお勧めします。また、以下2~5についても専門家のご紹介や、不安な点の解決に向けてご支援させていただきます。
2.寄付先・課題を選ぶ
ご自身が寄与したい社会課題や、その解決に取り組む団体を選定します。不動産など金銭以外の遺贈寄付を検討する場合は、事前に団体に現物でも受け付けてもらえるのか、確認しておくことをお勧めします。
3.財産配分を決める
まずは、ご自身の保有財産を洗い出して、全体的な配分を検討します。ご家族などの法定相続人への相続財産と、遺贈寄付をする財産をどれにするか等 検討します。
4.遺言書を作成する
これまで取り決めてきた内容で、遺言書を作成します。遺言書の作成は、法的に有効なものであることと、着実に執行されなければ意味をなさないので、専門家のサポートを受けながら作成することをお勧めします。
5.亡くなった後に遺言が執行される
ご自身が亡くなったのち、遺言執行者によって、遺言に示されていた内容に基づき相続の手続きを取り行います。ご本人が亡くなったことが遺言執行者に確実に伝わるように、信頼できる方にお願いしておきましょう。
よくある質問 Q&A
遺贈寄付に関してよくある質問に、全国レガシーギフト協会の専門家チームが回答します。
私たちについて
公益財団法人佐賀未来創造基金は、地域の困りごとの解決をはじめ、新しい価値を創造するために、皆様からのあたたかい「遺贈寄付」を地域の基金を創り、CSO(市民社会組織)等の担い手をはじめ、奨学金などの必要とされている地域の皆さまにお繋ぎしていきます。
<お願い>
当センターは相続や遺贈に関する「税務」や「法務」、またいわゆる利益を目的とした「資産運用」の相談窓口ではありません。
ご相談いただく内容によっては、法律上お答えしかねる場合がございますので、税務や法務等の専門的なアドバイス等が必要となる場合は、我々が連携している税理士、弁護士等の専門家や、金融機関等、行政窓口等へおつなぎするか、またはご自身でお尋ね頂くこととなります。